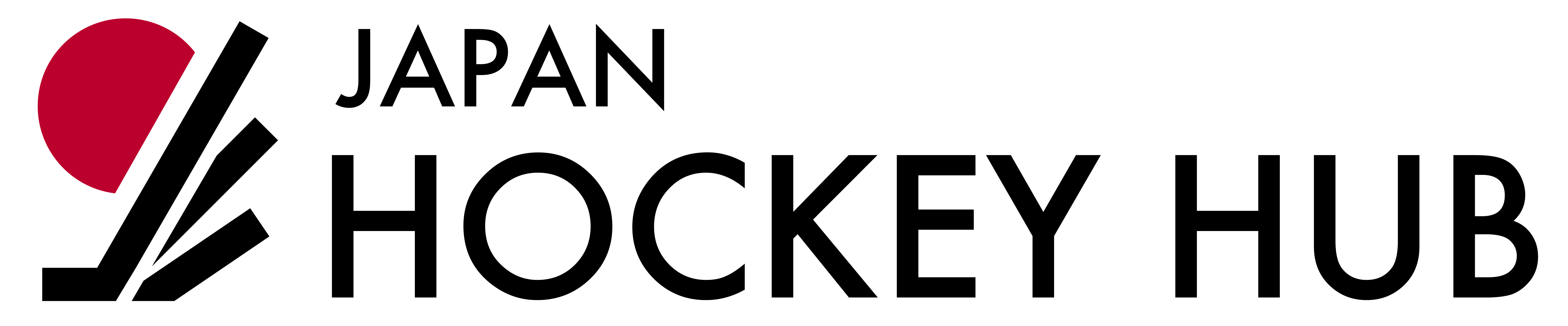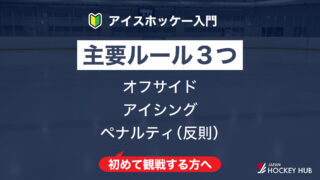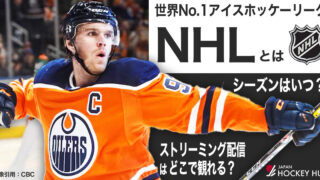アメリカの大学スポーツは、世界でもトップレベルの競技環境を誇り、まるでプロ選手のように学生アスリートたちが脚光を浴びています。
その中でも、NCAA(全米大学体育協会)のディビジョンⅠ(NCAA D1)アイスホッケーリーグ は、NHLを目指す選手にとって重要な登竜門のひとつです。
今回は、NCAA D1アイスホッケーの仕組み、NHLへのステップ、奨学金制度、卒業後の進路 など、D1の実態について詳しく解説します。
まず、NCAAとは?

NCAA(National Collegiate Athletic Association)は、アメリカの大学スポーツを統括する組織であり、アスリートの育成と競技の公平性を確保する役割を担っています。
NCAAにはディビジョンⅠ(D1)、ディビジョンⅡ(D2)、ディビジョンⅢ(D3)の3つの階層があり、D1が最上位、D3が最下位に位置します。
それぞれの大学は、財政規模やスポーツプログラムの充実度に応じてディビジョンに振り分けられ、さらに地域ごとにカンファレンスに編成されます。
NCAAにはアイスホッケー以外にも、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球など、多種多様なスポーツが含まれています。
ただし、全ての大学が全てのスポーツを提供しているわけではなく、大学ごとに異なる競技プログラムを有しています。
また、大学のカンファレンス編成は競技ごとに異なることもあります。
D1の大学は一般的に財政力があり、学生数の多い総合大学が多い傾向にあります。
一方、D3では小規模なリベラルアーツカレッジ(教養を重視する大学)が多くを占めます。
学業(アカデミック)に関しては、D3の大学が必ずしも学業レベルが低いわけではありません。
例えば、D3にはアカデミックランキングの高い大学も多く、ディビジョンの分類は競技面の基準で決まるため、学業レベルと必ずしも一致しない点が特徴です。
アイスホッケー競技においてはD2がない

アイスホッケー競技は、運営に多額の資金が必要です。
NCAA加盟校は約1,100校ですが、アイスホッケー競技チームを保有する大学はその中でも160校のみ。
そうしたアイスホッケー競技チームを有する大学の少なさから、NCAAアイスホッケー競技には、D1とD3が存在しますが、男女ともにD2が存在しません。
64校がD1で、96校がD3でアイスホッケー競技をプレーしております。
よって、アメリカ大学アイスホッケーの2部レベルの立ち位置にD3があります。
これらの理由から、『D3の中ではアイスホッケーが一番盛り上がっている』とD3所属のNew England Collegeを卒業した横浜GRITS GK 31番 冨田開選手はNoteで綴っています。

僕が生まれる前にはアイスホッケー競技にもD2があったらしいよ!
でも、D2レベルでアイスホッケー部を有する学校が少なくなったみたい…。
大学自体はD2に所属しているが、アイスホッケー部だけD3に属してプレーしている、みたいな大学もいくつかあるみたいです。
NCAA D1はNHLの登竜門!

NHLにドラフトされた後にすぐにNHL入りするケースは非常に稀で、ごく一部のトッププレイヤーに限られます。
アメリカ人の多く(とカナダ人の一部)はNHLドラフトで指名された後も、NCAA D1で経験を積んでステップアップしてからNHL、または育成リーグのAHL入りすることが多いです。
NHL選手の3人に1人がNCAA D1出身者
NCAAディビジョンI(D1)は、多くのNHL選手を輩出する登竜門としての役割を果たしています。
Let’s play Hockeyによると、NHLの2024-25シーズン開始時にNHLチームのロスターに名を連ねていた712名の選手のうち、約34%の242名の選手がNCAA D1出身選手でした。
つまりはNHL選手のおおよそ3人に1人はNCAA D1出身者ということです。

対して、カナダの大学リーグ出身のNHL選手はめちゃめちゃ希少!
NCAA D1アイスホッケーリーグは、世界の大学アイスホッケーの中でもずば抜けてハイレベルで盛り上がっているんです!
中退しても復学のハードルが低い
NCAAには、一度退学しても、取得した単位を引き継いで数年後に次の学期から復学できる制度を持つ大学がほとんどです。
この制度はアスリートにとって非常に大きなメリットがあります。
大学で早期にプロレベルに達した場合、卒業前に中退してプロデビューし、プロとしてのキャリアを終えた後に、必要であれば大学に戻って卒業するという選択肢を取るアスリートも少なくありません。
NCAA出身の現役NHLスター選手たち
▼こちらの記事で、NCAA出身の現役NHLスター選手たちをまとめております。
いかにNCAAから素晴らしい選手が輩出されているかがわかりますね!
プロ並みの環境でプレーができる

NCAA D1では、ほとんどの大学が自前のリンクを保有しており、そこでホームゲームを開催します。
ChatGPTのDeepReserchに調べてもらったところ、
D1アイスホッケーの64校のうち、54校がキャンパス内に自前のリンクを保有し、そこでホーム戦を行うようです。
(キャンパス内に自前のリンクを保有していない10校は、市内にあるリンクを借りて試合を行うそうです。)
そのため、多くの大学生が応援に駆けつけ、プロの試合さながらの熱気に包まれます。

例えば、オハイオ州立大学(Ohio State University)は2万人近くのキャパシティを誇る、バスケットボール兼アイスホッケー用のアリーナであるSchottenstein Centerを持ちます。

プロでなくとも、こんなリンクで若い大学生に囲まれて試合できることを想像したら、最高じゃないですか!?
また、試合のテレビ放送やインターネット配信も一般的で、特に全米王者を決めるFrozen Fourは全米で生中継され、アイスホッケーファンを熱狂させます。
加えて、NHL並みのトレーニング施設やリンクを完備していたり、専門のトレーニングスタッフ・メディカルスタッフによる栄養管理やメディカルサポートも充実しています。
転学(Transfer)も可能
NCAAでは他の大学に転学(Transfer)することも認められており、より良い環境やプレータイムを求めて移籍する選手もいます。
この際、単位がしっかりと引き継がれるので、学業の心配なく、打ち込んでいるスポーツを優先して転学することができます。
ほとんどの転学が同じディビジョン内で行われますが、場合によってはD1の大学で良い結果が出せず、より活躍できる環境を求めてD3の大学に転学するというケースもあります。
(逆のD3からD1は見たことがない…多分ほぼ行われないはず…。)
日本代表としてプレーした経験のある佐藤航平選手(28)も、NCAA D1時代はニューハンプシャー大学(University of New Hampshire)から同じくD1のベントレー大学(Bentley University)に転学した経歴があります。

コロナ禍の特別措置で、5年目までNCAAでプレーできるようになっていた
NCAAのアスリート奨学金
D1のアスリート奨学金は全額保証可能「フルライド」が可能
D1の大学は、最も競技レベルが高く、スポーツプログラムも充実しています。そのため、「フルライド」と呼ばれる全額奨学金を提供することが可能です。
D1の大学は、優秀なアスリートを確保するために多額の予算を投じており、特にアイスホッケーのような人気競技では、多くの選手がフルライド奨学金を受けています。

アメリカの大学は学費がめちゃめちゃ高い!!
だから、この学生アスリートたちは、奨学金の枠を争ってジュニアリーグや高校リーグで必死に戦うのです。
基本的にD1大学に行く選手はみんな奨学金を受け取っていますが、選手によって受け取る額(免除される額)が違うみたい。
中には奨学金を受け取ることができなくても、D1という最高な舞台を求めて自費で大学に通う選手もいるみたい…(Walk in:ウォークイン、というらしい)。
D2のアスリート奨学金は「部分保証」
D2の大学もアスリート奨学金を提供できますが、部分奨学金(パーシャルスカラシップ)が中心です。D1ほどの予算が確保されていないため、授業料の一部や生活費の一部が支給される形が一般的です。
D2の大学は、スポーツと学業の両立を重視する傾向があり、アスリートには競技と学業のバランスが求められます。
D3はアスリート奨学金が無く、普通の学業奨学金のみ
D3の大学では、スポーツ能力に基づく奨学金の提供が禁止されています。
そのため、D3のアスリートは学業メインでの奨学金や経済支援によって学費を賄うことになります。
ただし、D3の大学でも学業奨学金や助成金は充実している場合が多く、アカデミック面での優秀さを活かせば、経済的支援を受けられる可能性は十分にあります。
NCAAディビジョンⅠでプレーするためには?
▼2024-25シーズン現在、NCAAでプレーしている日本人選手たち
▼過去にNCAAディビジョンⅠでプレーしていた日本人選手たち
高卒であること(飛び級可能)
まずは当たり前ですが、高校を卒業していないとNCAAの大学に進学することはできません。
しかし、アメリカの大学進学は、日本と比べて時期の選択肢が多く、幅広いタイミングで行われています。
日本では「高校を3年で卒業し、18歳ですぐに大学に進学するか、1年・2年浪人して19歳・20歳で大学に進学する」というのが慣習として多くの人々が行なっていることですが、
アメリカでは以下のように、個人の適切なタイミングで大学に進学することができます。
ケース①:飛び級17歳で大学に進学する、世代を代表するようなジュニアトップ選手
(特にUSNTDPで育成されたトップ選手に多い)
ジュニアリーグ(16歳〜20歳)ではもう十分すぎるほど活躍をし終え、次のステップ(NCAA)に進みたい という選手は、高校を他の人よりも早期で終了し、17歳でNCAAの大学へ進学。
もちろん、早期で高校卒業するために、スポーツだけでなく勉強も他の人よりも勤勉に行う必要がある。
▼こちらの記事で紹介したQuinn Hughes、Jack Eichel、Macklin Celebriniのようなスター選手は、17歳でNCAAに進学しました。
ケース②:ジュニアリーグで最後までプレーした後、20歳・21歳で大学へ進学した一般的な選手
ジュニアリーグでは中程度くらいの活躍。
早い段階でNCAA大学アイスホッケーリーグに進んでしまうと、体格や技術が足りずに試合に出させてもらえない可能性がある。
なので、ジュニアリーグで年齢制限ギリギリまで経験を積み、20歳になってジュニアリーグの対象年齢でなくなってから、NCAAの大学へ進学。
学業の成績も良好であること

高卒であることだけでなく、学業の成績が基準に達しない選手は、入学すらさせてもらえません。
まず、NCAAが承認したコアコース(主要な教科)、
例えば、英語や数学、自然科学または物理化学、社会科学など、16のコースを高校卒業前に修了している必要があります。
また、これらのコアコースのGPA(成績平均点)が2.3以上である必要があります。
加えて、多くの大学は入学前に共通テストSAT・ACTのスコアの提出を学生に求めており、その出来によって大学入学の可否、そして奨学金の範囲の決定がなされます。
また、留学生であればTOEFLの成績の提出も求められるでしょう。
そして入学した後も、基本的にはGPA2.0以上を維持していないと試合に出場できなくなり、奨学金も撤回されます。
(この基準はカンファレンスや大学によって異なるらしく、優秀な大学が集まったアイビーリーグであれば、この基準がさらに高まるようです。)

実際に、高校のコアコースの成績が悪かったり、共通テストやTOEFLの結果が悪かったり、在学中にGPAの基準を維持できずに出場資格が剥奪されたケースは山ほどあります。
大学としてもNCAAとしても、ただのアスリートを育成・輩出するのではなく、人間としても一流の学生アスリートを育成・輩出するというビジョンを掲げているのでしょう。
大学からのオファーと、それに対するコミットメント(commmitment)

NCAAでは、その大学に進学する全ての生徒に、その大学チームでプレーする権利があるわけではありません。
大学からオファーがあり、そのオファーを承諾した選手のみがその大学チームでプレーすることができます。
基本的には、その選手がジュニアリーグでプレーしている間に、大学チームのスタッフ陣からオファーが出され、その後にその選手や家族、場合によってはその選手に雇われたエージェントと大学チームスタッフ陣との間で、緻密な話し合いが行われます。
具体的には、将来のビジョン、生活環境やサポート体制、奨学金の額の交渉、学業要件や専攻選択などについてが話し合われます。
双方の合意に至った際には、入学年度が確定していなくとも、コミットメント(Commitment)という形で公表されます。
ジュニアリーグや、そのリーグに属するチームのSNSをフォローしていると「〇〇選手が△△大学(D1)へコミット!」みたいな感じの投稿を見かけますね。かなりおめでたいことですからね。
▼2022年にアメリカTier2ジュニアリーグNAHLのLone Star Brahmasでプレーしていた日本人の村上レイ選手が、NCAA D1のナイアガラ大学(Niagara University)にコミットした際のチームのInstagram投稿
しかしこれは、口約束でしかなく、選手が大学へのコミットメントを発表したからといって、入学が確定したわけではありません。
先述のように学業の成績が足りなくて大学への入学か不可能になった場合や、双方の合意によって入学コミットが撤回される(Decommitment:デコミットメント)こともあります。
例えば、現在アジアリーグのレッドイーグルス北海道で活躍する安藤優作選手は、アメリカTier1ジュニアリーグUSHLで活躍した2019-20シーズンの終わりに、NCAAディビジョンⅠ の強豪校である ミネソタ州立大学マンケート校(Minnesota State University Mankato)へのコミットメントを発表しました。
彼は当時16歳で、リーグ最年少でありながら素晴らしい結果を残していたため、NCAA D1大学からオファーが来るのも納得です。
しかし、彼はジュニアリーグでの活躍を終えた2024年、コミットしていた大学へは進学せずに、レッドイーグルスへ入団しました。
彼がなぜ大学へ進学しなかったか(もしくはできなかったのか)の理由は不明ですが、このようにコミットしていたとしても、その入学は決して約束されたものではないのです。
どのジュニアリーグでプレーすれば、NCAA大学からのオファーをゲットできる?
NCAAの大学からオファーをゲットするためには、ほとんどの場合、北米の主要ジュニアリーグ、または高校リーグで活躍する必要があります。

北米以外でプレーしている選手にNCAA大学がオファーを出すことはほとんどないよ!
▼過去にNCAAディビジョンⅠでプレーしていた日本人選手たち3名は、みんな北米の主要ジュニアリーグ出身です。
NCAAディビジョンⅠ 大学へ行きたい場合
世界最高峰の大学リーグNCAA D1でプレーする選手のほとんどは、アメリカTier1ジュニアリーグUSHL出身の選手です。
USHLでプレーする選手のほとんどはNCAA D1の大学へ進学します。

これは噂でしかないですが、
USHLで1試合プレーしただけで、いくつかのNCAA D1大学からオファーが来た、みたいな事例があるらしいよ…。
NCAA D1とUSHLには強い結びつきがありますが、決してUSHLの選手だけがNCAA D1の大学に進学できるわけではありません。
アメリカTier2ジュニアリーグのNAHLや、独立リーグでTier2レベルとみなされているNCDCからも選手が数十名、NCAA D1の大学へ進学します。
そしてカナダに目をやれば、カナダ・ジュニアAリーグからも毎年多くの選手がNCAA D1の大学へ進学します。
特に、カナダ・ジュニアAリーグの中でもBCHLやAJHL、OJHLからのNCAA D1への進学率は高いです。
逆に、アメリカTier3ジュニアリーグのNA3HLや、Tier3とみなされているNCDC下部のUSPHL、カナダ・ジュニアBリーグから選手が直接NCAA D1大学への進学することほとんどあり得ません。
それぞれのリーグのNCAA D1コミット数を不等式で表すとこんな感じになります。
(僕の個人調査)
USHL >>> BCHL > NAHL = AJHL > NCDC = OJHL >> SJHL = MJHL
> 他のカナダ・ジュニアAリーグ > アメリカTier3ジュニアリーグ = カナダジュニアBリーグ
卒業後の進路:NHL・AHL・ECHL、もしくはヨーロッパへ
NCAA D1でプレーした選手の多くは、卒業後にプロへ進みます。
NHLドラフト指名選手はNHL・AHL・ECHLへ

すでにNHLドラフトで指名されている選手は、卒業後すぐに、その選手をドラフトしたNHLチームとEntry Level Contract(ルーキー用の、NHL・AHL・ECHLの全てでプレー可能な契約)を契約することが多いです。
一部のスター選手は直接NHLデビューを果たしますが、多くの選手はまずAHLで経験を積んでからNHLに昇格します。
(もちろんECHLで経験を積むドラフト選手もいるけど、AHLでプレーする選手の方が多い印象。)
また先述の通り、卒業を待たずして中退し、プロの道へ進む選手も多いです。
フリーエージェントの選手もプロの道へ
NHLドラフトで指名されなかった選手でも、フリーエージェントとしてNHLやAHLと契約することが可能 です。

ドラフト対象年齢を過ぎてからNCAAでめちゃめちゃ成長した才能が光る選手を獲得するために、NHL各チームのスカウトマンが目を光らせているよ!
例えば、以下の2選手はNHLドラフトで指名されなかったけど、NCAAでの活躍が脚光を浴びて、NHLチームと契約し、今の地位を確立したんだ!
▼Tronto Maple LeafsのベテランDFのChris Tanev

▼Winnipeg Jetsのアシスタントキャプテンで攻撃的DFのNeal Pionk

しかし、上記のような、フリーエージェントでNHLで契約する選手は圧倒的少数派。
また、卒業後すぐにAHLチームと契約できる選手も、良い成績を残したごく一部の選手たちだけです。
多くの選手は、フリーエージェントでECHLチームと契約してプレーします。
加えて、ヨーロッパ強豪国のTier2・3プロリーグであれば、NCAA卒業後すぐに契約してプレーする選手も少なくないですが、かなり少数派です。
卒業後、普通に就職する人も
ごく一部ですが、NCAA D1で活躍した後にプロ選手にはならず、自分が取得した学位の分野で普通に就職する人もいるようです。
D3であればその割合はかなり大きくなります。

やはりプロの世界は厳しい。セカンドキャリア問題もありますからね…。
下位リーグのプロ選手になるよりは、取得した学位を生かして就職する方が経済的には得なのは、万国共通なんですね。
NCAAを観戦する方法
ストリーミング配信は統一されておらず…
NCAAアイスホッケーの試合は、リーグで統一されたストリーミングサービスで放送されているわけではなく、カンファレンスによってその視聴方法が違います。
D1の有名カンファレンスの試合であればTVのESPNチャンネル、またはその姉妹チャンネルであるESPN2、大学スポーツに特化したESPNUで放送されることが多いようです。

2025年の全米ナショナルトーナメントの日程と放送チャンネル。やっぱり全てESPN系列ですね。
また、インターネットライブストリーミングサービスであれば、ESPN+で視聴が可能です。
D3の試合はTV放送されることはあまりないようです。
ただ、AHL・ECHLの試合も視聴可能なFloHockeyというインターネットストリーミングサービスでいくつかのNCAA D3の試合も放送されることがあるようです。
YouTube配信(統一されていないけど)
D1の有名カンファレンスの試合や強豪校の試合であれば、NCAA Hockey Highlightsというチャンネルにて無料YouTubeハイライトやアーカイブ配信が視聴可能なようです。
しかし、NCAA全ての試合のハイライトを配信しているわけではないようです。
▼2024年Frozen Four(全米チャンピオンシップトーナメント)決勝戦のハイライト動画
▼2025年 NCAA女子の決勝戦 – 女子も盛り上がり半端ねぇ…
D3の試合も、たまにYouTubeでハイライト動画やアーカイブ配信がされているみたいです。
まとめ:NCAA D1ホッケーを知れば、アイスホッケーがもっと楽しくなる!
- NCAA D1は NHLの登竜門 であり、プロ並みの環境でプレーできる
- 多くの選手はUSHLなどのジュニアリーグを経てNCAAへコミット
- 学業の成績も重要で、奨学金制度があるため学費の負担が軽減される
- 卒業後はNHL・AHL・ヨーロッパリーグなど、多くの選手がプロへ進む
- 日本からでもESPN+やYouTubeで観戦可能
未来のNHLスターをいち早く発見したい方は、ぜひNCAA D1ホッケーの試合をチェックしてみましょう!
このブログについて

このブログでは、アメリカでプロアイスホッケー選手として活躍する僕もんじが、
- アイスホッケー初心者に向けて
- 超絶わかりやすくルール解説
初心者向けルール解説の記事をまとめたカテゴリーはこちら - アイスホッケーの色々な豆知識
- 超絶わかりやすくルール解説
- アイスホッケーファンに向けて
- 日本や世界のアイスホッケー事情を紹介
世界のアイスホッケーに関する記事をまとめたカテゴリーはこちら - さらにアイスホッケーが面白くなる情報の発信
- 日本や世界のアイスホッケー事情を紹介
を行なっております!
アイスホッケーは超絶面白い!
アイスホッケーをより楽しんでいただくために、こちらのブログを是非お読みくださいね💪